加熱発泡機構モデル 風化によりNa+が H+と交換している表面層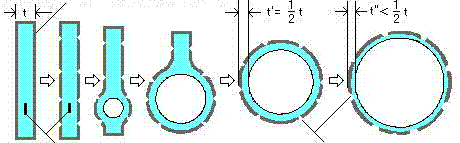
クリスタリット等の不純物 溝状亀裂
①室温②500°C③900°C ④950°C ⑤1000°C ⑥発泡終了
| 加熱ステージによる観察 粒度:約 0.2mm昇温速度:約1000°C/min  |
| ① | 火山ガラス質堆積物に含まれる火山ガラス自然粒を加熱すると、 |
|---|---|
| ② | 約 500°Cで表面層のHイオンが粒子外に拡散し、収縮のため表面に亀裂が発生する。 |
| ③ | 約 900°Cになると、Naイオンの濃度勾配があるため、粒子の内部が表面層より先に軟化し、クリスタリットやミクロポアなどの異物を核として気泡が発生し、両端はひれ状になる。 |
| ④ | 約 950°Cでは、表面層は Naイオンが少ないため硬いので、粒子の端面付近に気泡が発生しても、気泡は内部のひれ状の方向に膨張を続け、 |
| ⑤ | 約 1000°Cになると、表面の硬い層が発泡体の表面層となり、また、表面層だけ硬いので球形となり、 |
| ⑥ | 表面層の亀裂の部分を両側に広げるような形で膨張する。 |