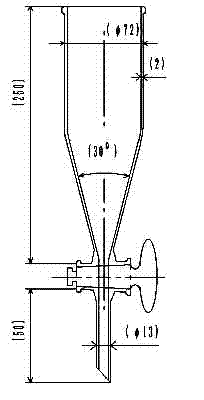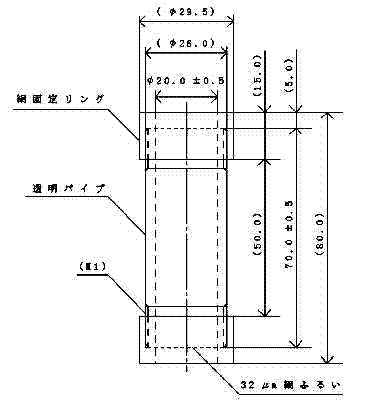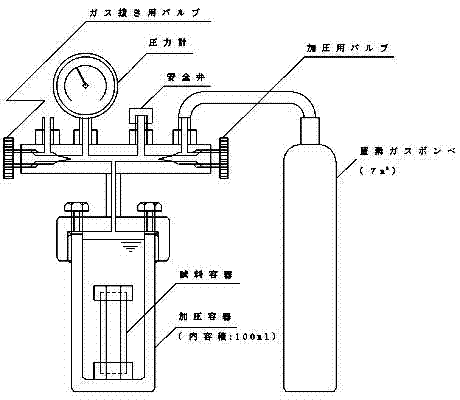| この解説は、本体に規定した事柄、参考に記載した事柄、並びにこれらに関連した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。
|
|
|
| 1. | 審議経過
|
| 1.1 規格の名称
|
| 本規格の名称として、“微細中空ガラス球状体”の名称も考えられたが、人工原料から生産され、また、シラスバルーンとは化学組成も異なるものがあるため、採用しなかった。
人工原料から生産されているものと区別するため、通称として使用されている“シラスバルーン”の名称を採用した。
|
| 1.2 パーライト(JIS A5007)との関係
|
| シラスバルーンは、パーライトと異なり、火山ガラス質堆積物あるいはガラス質凝灰岩を原料として製造されており、品質的には、一部パーライト規格で規定されている範囲に含まれるものもあるが、全体としてはるかに微粒であり、用途も異なる場合が多いので、シラスバルーン単独の標準規格案を作成することになった。
|
| 1.3 浮揚率
|
| 発泡の程度を表す指針としては、かさ密度の他に、直接水中に投入して浮揚する量を用いることがある。
液中に分散して複合材料を生産する工程などで、液に浮揚する割合が工程管理上、必要になる場合もある。
また、シラスバルーンのような微細中空ガラス球状体の強度を現す指標としては静水圧浮揚率がある。
これらの浮揚率の規格化に関しては、原案作成委員会で全会一致の合意を得なかった。
しかし、統一した測定法として残す必要性があることから、参考として記載した。
|
| 2. | 逐条解説
|
| 2.1 適用範囲
|
| 規格に記載した用途以外に、化粧品、教材用紙粘土、爆薬の増感剤等、数多くの利用がなされているが、量的に多いものを例として記載した。
|
| 2.2 製造方法
|
| 規格に記載した火山ガラス堆積物質あるいはガラス質凝灰岩は、北海道、東北、南九州地方等に広く分布している。
火山ガラス質堆積物は、北海道、東北地方では火山灰、南九州地方ではシラスと呼ばれている。
ガラス質凝灰岩は、産地により呼称は様々であるが、多くは白土と呼ばれている。
|
| 2.3 種類および呼び方
|
| 2.3.1 かさ密度
|
| かさ密度に関する表現は、かさ密度、かさ比重、見掛け密度、見掛け比重、単位容積質量あるいは見掛け比容など様々である。
JIS A5007では単位容積質量、JIS K3362では見掛け密度、JIS K5101では見掛け密度または見掛け比容、JIS A6721ではかさ比重、JIS K6891では見掛け密度、JIS R6126ではかさ比重、JIS Z2504では見掛密度を採用している。
JIS Z8202では、付表3力学の表に密度、比重の記載があるが、注記として“比重はISO 31/3-1978には記載されていない”と記載されている。
このことから、本規格では、“密度”を採用した。
また、シラスバルーンのように中空の粒子は、見掛け密度の表現を用いると、1個1個の粒子の密度と混同される場合が多い。
一方、“粉体−理論と応用−”、“セラミック工学ハンドブック”等では、粉体を容器に充填した体積と質量から計算される密度は、“かさ密度”の表現を用いている。
このようなことから、本規格では、“かさ密度”を採用した。
|
| 参 考
|
| JIS A5007-1977 パーライト
|
| JIS K3362-1990 合成洗剤試験方法
|
| JIS K5101-1991 顔料試験方法
|
| JIS K6721-1977 塩化ビニル樹脂試験方法
|
| JIS K6891-1977 四ふっ化エチレン樹脂成形粉試験方法
|
| JIS R6126-1970 人造研削材のかさ比重試験方法
|
| JIS Z2504-1979 金属粉の見掛密度試験方法
|
| JIS Z8202-1985 量記号、単位記号及び化学記号
|
| 久保輝一郎、神保元二、水渡英二、高橋浩、早川宗八郎編“粉体−理論と応用−”p.341、丸善(1979)
|
| 社団法人日本セラミックス協会編“セラミック工学ハンドブック”p.63、技報堂出版(1989)
|
| 2.3.2 粒度
|
| 粒子の大きさと分布によってA〜Lの12区分とした。
|
| 2.4 試験
|
| 2.4.1 かさ密度
|
| かさ密度は、静的測定方法と動的測定方法がある。JIS A5007では、静的測定方法を採用している。
一方、JIS K5101では、両者を採用しているが、顔料試験方法に関するISO規格では、動的測定法だけが規定されている。
シラスバルーンのように軽量・微粒のものは、静的測定法は、測定容器に充填する方法の差異により、かさ容積が著しく異り、また、再現性も悪いので、動的測定方法を採用することにした。
なお、参考例として、かさ密度の異なるシラスバルーン6試料(a〜f)を用いて、静的測定法と動的測定法により測定した結果を解説表1に示す。
|
|
解説表1 静的測定法と動的測定法により測定したかさ密度(g/cm 3)の例
| 試 料 | 静的測定法 | 動的測定法
|
|---|
| a | 0.07 | 0.09
| | b | 0.12 | 0.19
| | c | 0.14 | 0.19
| | d | 0.21 | 0.30
| | e | 0.27 | 0.33
| | f | 0.31 | 0.36
|
|
|
|
| 規定したタッピング装置の条件を満たす装置の一例としては、JIS K5101 図22の見掛け密度または見掛け比容測定器の一例(タップ法)がある。
また、規定した容量のメスシリンダーを、JIS R5201 参考図7のフローテーブルの中心に固定しても良い。この場合、手動で規定条件を満たすように回転ハンドルを回転させるか、規定速度で回転するように電動機を用いて回転させ、規定回数で停止するスイッチにより停止させることも可能である。
このようなことから、タッピング装置に関しては、タップ高さ、タップ速度、タップ回数の条件だけを記載し、装置そのものの規定はしなかった。
|
|
| 参 考 |
|
|---|
| JIS A5007-1977 | パーライト
|
|---|
| JIS K5101-1991 | 顔料試験方法
|
|---|
| ISO 787/11-1981 | General methods of test for pigments and extenders -Part 11:Determination of tamped volume and apparent density after tamping
|
|---|
| JIS R5201-1987 | セメントの物性試験方法
|
|---|
|
| 2.4.2 粒 度
|
| 標準ふるいによるふるい分けは、乾式法と湿式法があるJIS A5007では、乾式法を採用している.シラスバルーンのように微粒のものは、乾式法ではふるい分けが困難であるので、湿式法を採用することにした。JIS K5101では、エタノールを用いた湿式法を採用しているが、水道水を用いる方法が一般的と考え、採用した。
一方、顔料試験方法に関するISO規格では、ふるい残分の残量の測定について、残量をふるいからはかり瓶に移す操作があるが、JIS K5101では、ふるいごと量る方法が操作ミスが少ないとして、採用している。
そこで、本規格でもふるいごと量る方法を採用した。
|
|
| 参 考 |
|
|---|
| JIS A5007-1977 | パーライト
|
|---|
| JIS K5101-1991 | 顔料試験方法
|
|---|
| ISO 787/7-1981 | General methods of test for pigments and extenders - Part 7:Determination of residue on sieve -Water method- Manual procedure
|
|---|
|
| 3. | 参考解説
|
| 3.1 試 験
|
| 3.1.1 水中浮揚率
|
| 浮沈分離器は、浮揚物と沈降物との分離が可能な分液漏斗あるいは分離管を使用する。
分液漏斗は、JIS R3503に規定する分液漏斗の中では呼び容量500mlのスキーブ形分液漏斗が、沈降物の排出が滑らかなので適当であるが、上部栓内径が小さく、試料の挿入と浮揚物の排出が困難である。
そこで、スキーブ形分液漏斗の上部を解放したガラス器具が好ましい。
この場合、コック栓の穴径は下部管の内径と等しくするのが望ましい。
一例として、スキーブ形分液漏斗の上部を解放したガラス器具を記載した。しかし、粒度が小さくなるに従って、浮揚物と沈降物の中間の水が透明になるまでに長時間を要するようになる。
短時間で分離が可能な、遠心分離機が使用できる浮沈分離管も市販されている.このようなことから、浮沈分離器は、様々な器具が使用できるように、“浮揚物と沈降物が分離できる透明ガラス製のもの”とした。
次項の静水圧浮揚率に関しても、浮沈分離器は、同様の理由から上記と同じ内容とした。なお、シラスバルーンの水中浮揚率は、種類あるいは製造方法によって異なり、20〜95wt%と幅広い。
|
| 参 考
|
| JIS R3503-1987 化学分析用ガラス器具
|
| 3.1.2 静水圧浮揚率
|
| 加圧装置は、ガス加圧、ポンプ加圧等があるので、規定圧力以上の圧力が得られるものとした。
一例として、ガス加圧方式の例を記載した。シラスバルーンの静水圧浮揚率は、水中浮揚率と同様に、種類あるいは製造方法によって異なり、5〜50wt%と幅広い。
なお、静水圧浮揚率を水中浮揚率で除して100倍した値は、水中浮揚物中の静水圧に耐えたものの割合を示し、この値が大きい物ほど、高強度の水中浮揚物を含んでいることを示す。
|
| 4. | 標準規格委員会の委員構成は、次のとおりである.
|
|
標準規格委員会 構成表(平成4年8月)
| 氏 名 | 所 属
|
|---|
| 委員長 | 木村邦夫 | 工業技術院九州工業技術試験所
| 平松博久 | 通商産業省生活産業局
| 地崎 修 | 工業技術院標準部
| 濱野健也 | 神奈川大学
| 諌山幸男 | 九州共立大学
| 神尾 典 | 工業技術院九州工業技術試験所
| 陣内和彦 | 鹿児島県工業技術センター
| 茂呂端生 | 財団法人日本産業技術振興協会
| 黒木勝也 | 財団法人日本規格協会
| 高橋昭彦 | 三機工業株式会社
| 山元和徳 | イヂチ化成株式会社
| 鳴海一夫 | 釧路石炭乾溜株式会社
| 関 博光 | 株式会社シラックスウ
| 篠塚昌毅 | 大建工業株式会社
| 木本潤一 | 株式会社カルシード
| 沼田四郎 | 社団法人日本塗料工業会
| 秋浜繁幸 | 株式会社 FRC
| 事務局 | 村川順之 | 株式会社リアライズ社(VSI 研究会事務局)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Last updated:September1,1999
| |